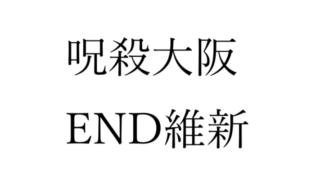 END維新
END維新 大阪府の道路予算削減と交通安全の現状
大阪府における道路予算削減は、交通安全に深刻な影響を及ぼしています。白線の消失や交差点の視認性低下が、事故の増加を招いていることは明らかです。今後は、住民の安全を第一に考え、予算の適切な配分と、持続可能な道路管理の仕組みを整えていくことが求められます。
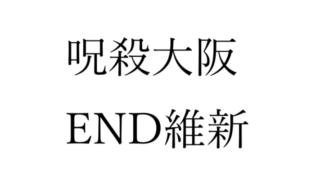 END維新
END維新 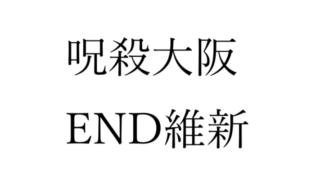 END維新
END維新 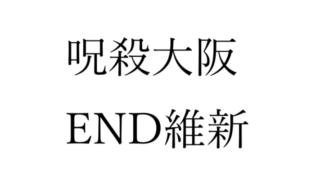 END維新
END維新 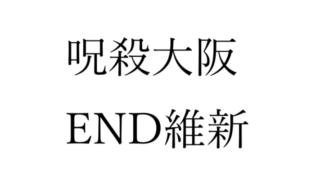 END維新
END維新 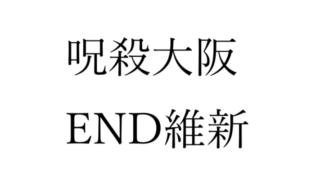 END維新
END維新 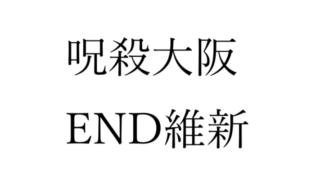 END維新
END維新 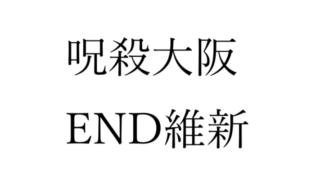 END維新
END維新 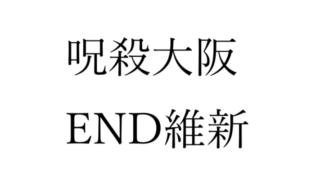 END維新
END維新 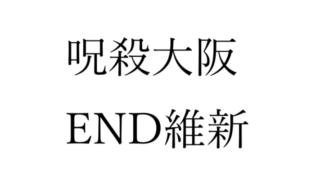 END維新
END維新 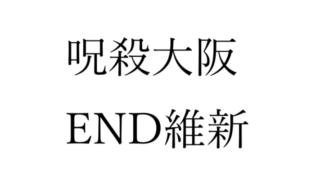 END維新
END維新