
2025年3月13日、日本医療労働組合連合会(日本医労連)の**「25春闘統一行動」が全国各地で展開されました。千葉県でも、千葉県医労連の組合員である看護師たちが医療現場の深刻な問題を訴えました。その声の根底には、「現場の疲弊」「賃金の低さ」「人手不足」**という日本の医療が抱える構造的な問題が横たわっています。本記事では、彼らの訴えをもとに、日本の医療労働の現状と今後の課題を考察します。
日本医労連25春闘統一行動とは?
日本医労連は、全国の病院や診療所、福祉施設などで働く医療労働者の労働条件改善を目指す労働組合です。毎年春に、医療現場の賃上げや労働環境改善を求める統一行動を行っており、これが**「春闘(春季生活闘争)」**と呼ばれています。
2025年の春闘では、**「賃上げ要求」「人員増」「労働環境の改善」**が大きなテーマとなり、全国で統一行動が実施されました。千葉県では、医療の最前線で働く看護師らが、過酷な現場の現状を訴えました。
千葉県医労連看護師組合員の訴えとは?
千葉県の統一行動に参加した看護師たちは、次のような問題を指摘しました。
賃金の低さと物価上昇
- 看護師の給料は決して高くなく、特に民間病院では厳しい状況が続いている。
- 近年の物価上昇に対して、給与がほとんど上がっていないため、生活が苦しくなっている。
- 「私たちの賃金が上がらないのに、物価だけがどんどん上がる。もう限界です。」(看護師A)
深刻な人手不足と長時間労働
- 看護師の過労死ラインを超える労働時間が問題視されている。
- 特に夜勤は過酷で、人員不足のために1人あたりの業務負担が増えている。
- 「夜勤が終わった後、クタクタなのに次の日もすぐにシフトが入る。何のために働いているのか分からなくなる。」(看護師B)
若手の離職率の高さ
- 新卒看護師の約1割が1年以内に退職するというデータもあり、人材定着が大きな課題。
- 「新人がすぐに辞めてしまう。教える人も疲れているから、誰も止められない悪循環が続いている。」(看護師C)
医療機関の経営問題
- 診療報酬の引き下げや病院の統廃合が進み、公立病院の経営が厳しくなっている。
- 「地域医療を支えているのは公立病院。ここが潰れたら、私たちはどこで働けばいいの?」(看護師D)
なぜこの問題は解決されないのか?
このような問題が放置されている背景には、政府の医療政策の方向性が関係しています。
診療報酬の抑制と公立病院の統廃合
政府は医療費削減を目的に、公立病院の統廃合や診療報酬の引き下げを進めています。その結果、病院側は看護師の給料を上げる余裕がなくなり、慢性的な人手不足が悪化しています。
医療労働の軽視
医療現場は「やりがい搾取」の典型例とも言われます。
- 「命を救う仕事だから」と、低賃金・長時間労働が正当化されてしまう。
- 「患者のため」という言葉で、過労を強いられる。
- しかし、医療従事者も人間であり、適切な労働環境が必要である。
政府の賃上げ政策が医療に反映されない
政府は「賃上げ」を推奨しているが、医療機関への財政支援は限定的。
- 医療は公的な要素が強いため、民間企業のように自由に賃上げできない。
- 診療報酬の引き上げなど、政府の介入が不可欠だが、後回しにされている。
今後求められる対策とは?
では、この状況を改善するためには、どのような対策が必要なのでしょうか?
診療報酬の見直しと公的医療機関の強化
- 診療報酬を適正に引き上げ、病院経営を安定させる。
- 公立・公的病院の統廃合を見直し、地域医療を守る。
看護師の賃金改善と労働環境の見直し
- 夜勤手当の増額や人員増による負担軽減が不可欠。
- 「看護師=長時間労働」の固定観念を見直し、ワークライフバランスを考慮した勤務体系へ。
医療現場の声を政策に反映させる
- 日本医労連などの労働組合の意見を尊重し、現場の声が届く仕組みを作る。
- 国会での議論を増やし、医療政策をより実効性のあるものにする。
まとめ:医療従事者を守ることは、社会全体を守ること
千葉県医労連の看護師たちが声を上げたのは、「自分たちのため」だけではありません。医療現場の崩壊は、最終的に患者や地域住民に大きな影響を与えます。
- 賃金を上げることは、看護師を増やし、医療の質を向上させることに繋がる。
- 労働環境を改善することは、患者にとってもより良い医療を受けられる環境を作ることになる。
この問題を「医療従事者だけの課題」として捉えるのではなく、社会全体の問題として考え、適切な政策が求められます。
「医療を守る=未来を守る」
今こそ、現場の声を政治に反映させ、医療崩壊を防ぐための行動を起こすべき時ではないでしょうか?

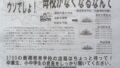

コメント